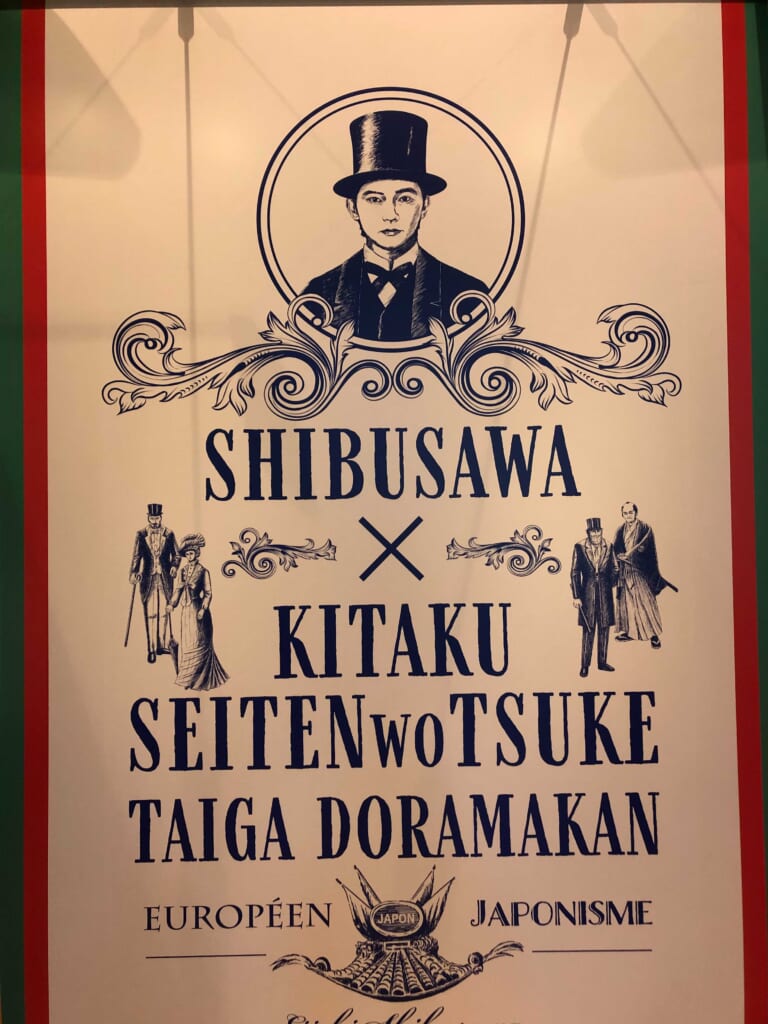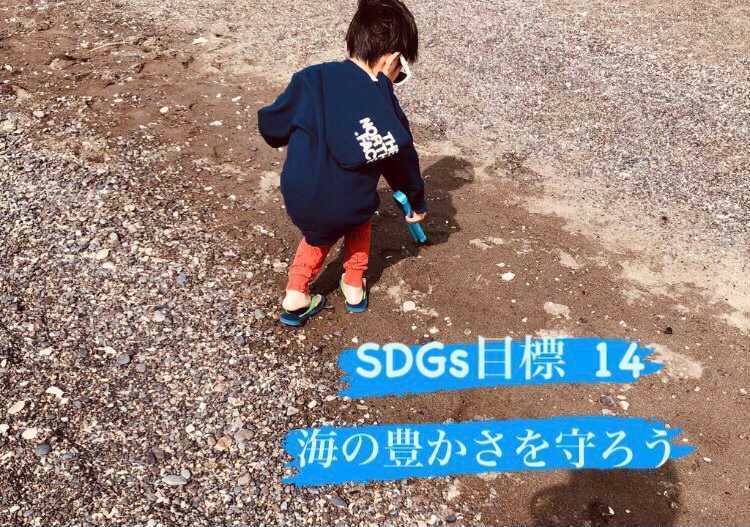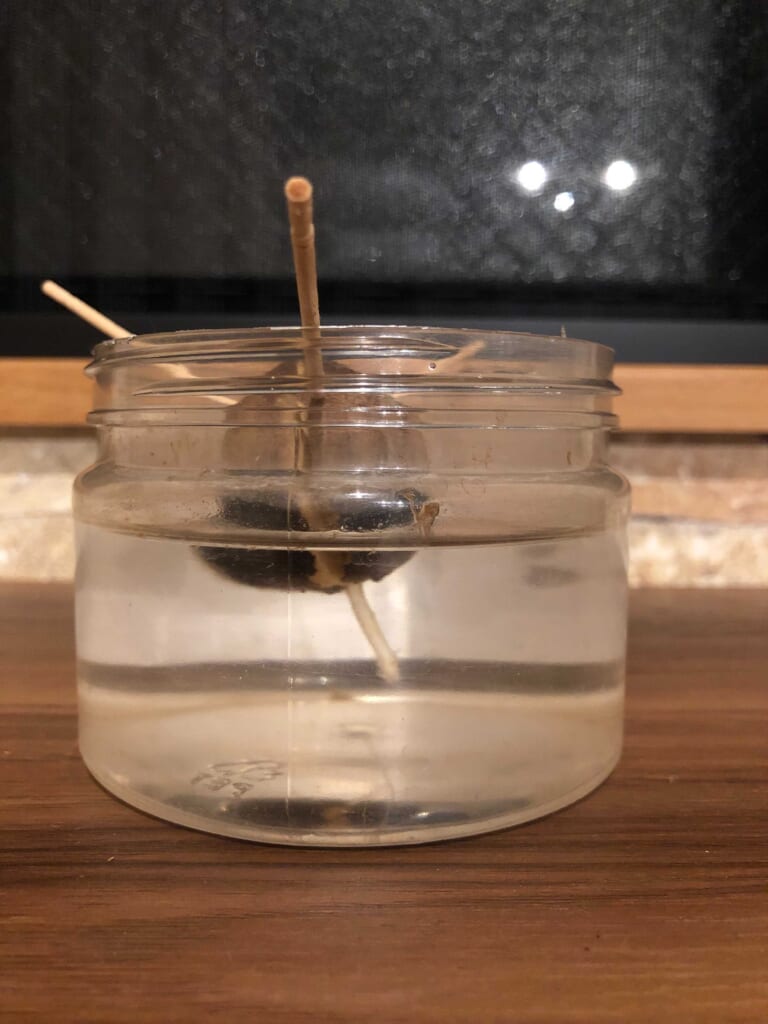ネットショップ運営において、広告費をかけるべきか、それとも最安値で勝負すべきか悩むことがあります。
以上をふまえて、手動ではなく自動で価格調査と価格更新をすべき理由とおすすめの方法についてお話します。
自社独自のオリジナル商品を扱っている場合は、認知度が低く検索でヒットしにくいので広告費をかけた方がよい でしょう。
認知度が高くなり購入が増えれば、購入したユーザからレビュー・口コミを書いてもらえる可能性もあり、商品とともにショップの評価も向上する効果も期待できる でしょう。
メーカー・型番の商品を扱っているショップの場合は、すでに認知度が高いため最安値で勝負した方がよい でしょう。
メーカーや型番で検索した際に、最安値に引っかからない場合や競合他店に価格で負けている場合は、選ばれにくいからです。
最安値、もしくは最低でも定価や相場より安い価格を提示することが購入につながります。
そもそも、広告は労力やコストが膨大です。その上で高い広告効果が得られないのであれば、時間も費用も無駄になってしまいます。
最安値で勝負すれば、検索結果に必ず反映 されます。価格調査を行い、最安値、もしくは最安値に近い価格に設定した方が、購入される可能性が高まり、売上もアップしやすい です。
次に、メーカー型番ショップでユーザーが購入するポイントについて解説します。
ユーザーは、基本的に商品価格のみならず、送料や付与されるポイントを含めた金額を見て選びます。同じ金額なら送料無料がお得に感じますし、ポイントの付与が多いショップで購入したい と考えるものです。
また、レビューや口コミが少なかったとしても「最安値であればこのショップで購入したい」 と考えてもらえる可能性があります。
ユーザーはショップの商品紹介ページのレビュー、口コミ、評価をチェックしています。できるだけ安心して信頼できるショップで購入したい という気持ちは当然のことです。
認知度が低いショップや商品の場合は、ユーザーに選ばれるためにもレビューを集める対策が必須 です。
購買意欲が高まっているユーザーは、すぐに商品が欲しいので、ユーザーは在庫が確保されているショップを選びます。
以前は購入できたショップであっても、在庫切れが長く続いてしまっていたり、在庫連動などのミスで在庫が無ければ、競合他店など別のショップで購入されてしまいます。
ユーザーは、いちから調べて購入するより可能であれば前回と同じショップで購入したいですし、人気商品などの売れ行きを把握し在庫確保ができるように努めましょう。
メーカー型番商品は、商品で競合との差別化ができないため、対応の良さや発送までのスピードが大事 です。
そのうえで、ユーザーは価格・送料・ポイントも含めた実質最安値で選ぶ傾向があるため、常に競合の価格・送料・ポイントをチェックし最安値を保つことでユーザーに選ばれやすくなります。
手動で最安値を設定するには、かなり手間がかかるという点について、詳しく解説します。
価格調査は、可能であればリアルタイムに競合を追跡し、状況に応じて自社の価格を更新することで最安値を実現できます。しかし、変動する競合他店の価格や在庫を把握するのは、現実問題として不可能 です。
作業的には複雑なことではなくても、四六時中見張っていることはできません。その労力やコストに見合った利益を得ることはできないため、手動および人力では難しいのが現実です。
価格調査は、商品数に比例して作業コストも増加します。また、調査対象を増やせば増やすほど同じく膨大な作業コストを要する ため、最安値に注力しすぎると時間や人的コストも負担がかかります。
最安値を維持できれば、ユーザーが検索して見つけてくれる機会も増えますが、手動および人力では難しいことを理解しておきましょう。
最安値の課題ですが、必ずしも利益を増やせるとは限りません。もし、手動および人力の作業において、ケアレスミスやヒューマンエラーによって原価割れを起こしてしまえば、マイナスになってしまうことも考えられます。
原価はショップによって異なるため、単純な最安値を追い求めすぎると価格競争に巻き込まれてしまい、売れても利益が出ず売上アップには繋がりません。
らくらく最安更新は、単なる最安値ではなく、利益が出る最安値で価格更新できるツールです。というのも、利益が出ない、もしくは、原価割れになる価格に自動で更新されてしまうと、利益がどんどん目減りしていきます。
らくらく最安更新であれば、価格調査の際に商品ごとの下限の価格を設定できるため、確実に利益が出る最安値による価格更新が可能 です。
らくらく最安更新は、24時間・365日・1日12回、システムの自動化で価格調査と価格更新を行ってくれるため、最安値を保ちやすく、アクセスが増え、売上に繋がることが期待できます。
手動であれば時間や労力のコストは膨大ですが、らくらく最安更新は自動更新されるので時間も労力も最小限であり、事務作業の負担を削減するとともに時間的な余裕と人的なリソースを確保 できます。
らくらく最安更新は、価格調査の際に上限や下限の価格を設定でき、除外するショップを指定できます。そのため、過度な価格競争に巻き込まれることなく、適切な価格を設定することが可能です。
一度設定してしまえば、競合他店やライバルショップを過度に意識せずに済むため、勝ち負けなどの心理的なストレスも大幅に軽減 されます。
らくらく最安更新は、最安ショップのデータが一覧で表示されるため、全体が把握しやすく業務効率もアップします。
また、各商品の最安値や自店舗との価格差も表示されるため、どの商品に注力すべきかも把握しやすくなり、仕入れる際にも役に立ちます。
らくらく最安更新は、検索結果から調査対象の最安値ショップが変わると 、価格に連動して値下げだけでなく値上げもします。
手動で価格調査をする場合は、リアルタイムに競合の価格を調査することが難しいです。しかし、値下げしたままでは競合他店と価格差がうまれ、機会損失になってしまいます。
らくらく最安更新であれば、自動で価格を調査し更新するため値上げもでき、機会損失もなく利益の最大化につながります。
今回は、メーカー型番ショップが広告費より最安値で勝負した方がいい理由、ユーザーが購入するポイント、そして手動ではなく自動で価格調査と価格更新をすべき理由とおすすめの方法についてお話しました。
らくらく最安更新なら、ランニングコストを抑えつつ、最安値によって利益の確保と売上アップへの近道につながります。今ですと無料ですべての機能を利用可能な「30日間のトライアル」 をお試しいただけます ので、興味をお持ちであれば、ぜひともこの機会に、お気軽にお申し込みください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が、ネットショップ運営において広告と最安値のどちらで勝負すべきかお悩みの方のお役に立てれば幸いです。